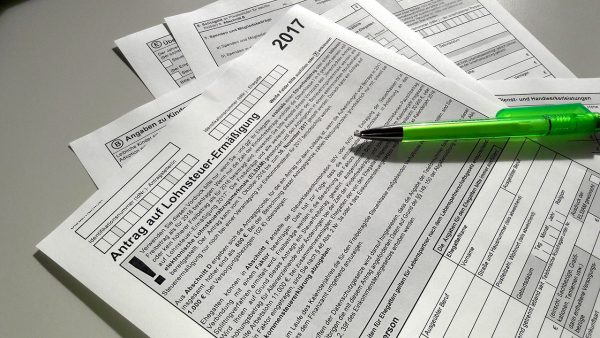- スタッフブログ (91)
- 仲介会社様専用ページ (1)
- 未分類 (5)
- 活動報告 (2)
- 2025年12月 (1)
- 2025年8月 (1)
- 2024年12月 (1)
- 2023年12月 (1)
- 2023年8月 (1)
- 2023年1月 (1)
- 2022年12月 (1)
- 2022年8月 (3)
- 2022年5月 (1)
- 2022年4月 (1)
- 2022年1月 (1)
- 2021年12月 (1)
- 2020年12月 (1)
- 2020年6月 (1)
- 2019年12月 (1)
- 2019年11月 (1)
- 2019年9月 (1)
- 2019年7月 (1)
- 2019年4月 (1)
- 2019年3月 (5)
- 2018年12月 (1)
- 2018年7月 (1)
- 2018年5月 (2)
- 2018年4月 (5)
- 2018年3月 (12)
- 2018年2月 (12)
- 2018年1月 (12)
- 2017年12月 (13)
- 2017年11月 (14)
- 2017年10月 (1)
オーナーによる自己回収事例
またまた、
2018.2.26発行の全国賃貸住宅新聞より記事をご紹介。
今回の記事では、
相続した賃貸物件に合計800万円の滞納があったのを、
オーナーが自分で回収された事例です。
多い方で滞納額が200万円もあったらしく、
オーナーが様々な手法をされて回収されています。
赤線の部分は私が良いなと思った箇所です。
相手に全額払えといってもすぐには無理なので、
いくら払えるかを約束したというのは良い方法
だと思います。
出来れば口約束でなく、
証文を交わす方が良いでしょう。
そして、
相手から危害を加えられないために
ファミリーレストランでお話をしたというのも
良い方法だと思います。
万が一の場合、
滞納者から暴行を受ける可能性もありますし、
虚言で滞納者から「オーナーから暴行を受けた」と
主張された場合にも、公共の場であれば
証人や防犯カメラでの立証もできます。
ご自分のリスクヘッジもされながら
話し合いで解決をされた良い例だと
思いましたので、ご紹介させて頂きました。
ルート・イノベーション スタッフブログ
繁忙期に行った入居促進対策
2018.2.26発行の全国賃貸住宅新聞より
ご紹介です。
現在繁忙期中の賃貸市場における、
1月~2月上旬までのアンケート調査結果が紹介されて
います。
気になった部分は、
管理会社が、どのような繁忙期対策をしているかという
点と、どのような賃貸傾向があるかという点
です。
繁忙期対策で最も多かったのが、
「フリーレント」となっています。
フリーレントとは、賃料無料期間のことですが、
例えば3.1に契約して、賃料発生は3.15から
というように、14日間の賃料を無料にする
方法です。
これは入居者にとって嬉しい方法ですので、
有効だと思います。
次いで多かったのが、
家主(オーナー)への賃料値下げ交渉でした。
そもそも割高の賃料設定ならば良いですが、
通常通り設定の場合には、あまり繁忙期序盤で
賃料値下げに応じるのもいかがかなと感じました。
※もちろん物件によりますが。
賃貸傾向については
大阪の業者様が
「法人はそうでもないが、外国人留学生の部屋探しが
増えている」との見解がありました。
弊社の場合、
もともと外国人賃貸事業を行っているので、
当然ながら外国人留学生の仲介は現在多いのですが、
通常の賃貸仲介店舗様にもたくさんお問い合わせが
あるようです。
また、記事内では
「外国人顧客様のリスクヘッジ」について
言及されていますが、
たしかに外国人のお客様には、特別なご説明が
必要になります。
ルールを守ってくださるかどうかは、
仲介店舗のご説明の仕方次第です。
この繁忙期に外国人受け入れを行う
オーナー様におかれましては、
仲介店舗への「説明の徹底」をお願いされること
をお勧めします。
ルート・イノベーション スタッフブログ
住宅ローン控除は確定申告しないと受けられない
2月16日から3月15日まで、
確定申告時期となっています。
平成29年に住宅ローンを利用して不動産購入を
された方で、
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)
を利用される方は、
確定申告を行わなければ適用されませんので、
注意が必要です。
住宅ローンを利用して購入された方でも、
全員に控除があるわけではありません。
築年数の要件や、
㎡数の要件があります。
例えば
住宅ローン控除を受けることが出来る
不動産の床面積は、登記簿上50㎡以上
でないと適用されません。
※パンフレット等に記載の面積(壁芯面積)
ではありませんので、注意が必要です。
詳細は国税庁HPをご覧ください。
なお、
宅建業者売主の物件を購入された方で、
一定要件を満たし、すまい給付金を
得られた方の場合には、
確定申告時に控除が必要なので、
ご注意ください。
ルート・イノベーション スタッフブログ
不動産買取という選択肢
不動産を売却する場合、
不動産市場にて売却する方法と、
買取会社に買い取ってもらう方法があります。
一般的に、
不動産買取は市場での売却と比較して
売却価格が安くなることが多く、
不動産買取業者に対して
悪いイメージをお持ちの方も
いらっしゃるかもしれません。
しかし、
不動産買取にはメリットもありますし、
買取業者が得ばかりしているわけでは
ないことをご説明いたします。
【不動産買取の売主様メリット】
・即資金化できる
・契約が流れる可能性が少ない
・1契約で通常2回会う手間が、買取の場合1回で済む
・近隣に知られずに売却出来る
・物件の瑕疵が免責になる
等
上記のようなメリットがあります。
そして、
不動産買取業者は得ばかりしているわけでは
ありません。
不動産買取業者は、
物件購入後、加工し、売却しますが、
宅建業法上、
自ら売主制限というものがあり、
宅建業者が売主として一般のお客様に
物件を売却する場合、
2年間は物件の瑕疵(見えない傷)について
面倒をみなければなりません。
売却後に
何かしらの物件の傷が発見された場合には、
対応しなければならないというアフターフォローが
義務付けられています。
また、
買取業者は購入して加工した物件が売却できなければ
利益はありません。
市況の変化や、近隣状況の変化により、
当初予定した金額で売却出来なくなる
場合もあります。
その結果、
マイナスになってしまうこともあります。
そのリスクも含めたうえでの
不動産買取です。
このように、
買取業者は得ばかりではないのです。
ですので、
不動産買取を打診されたお客様は、
提示された金額で納得できる場合には、
不動産買取に対する悪いイメージは無しにして、
ご検討されることをお勧めします。
ルート・イノベーション スタッフブログ
判例に基づいた記事のご紹介
以前、
の記事でも記載致しました通り、
事故物件の告知についての弊社スタンスは
変わりませんが、
2018.1.8発行の
全国賃貸住宅新聞に告知義務についての
記事が記載されていますので、
ご紹介させて頂きます。
こちらの記事では、
事故が生じた場合の責任は、
相続人や連帯保証人等へ追及出来る事や、
損害額の判断方法なども記載されています。
そして、
事故が起きたことを告知する期間については、
明確な告知期間は定まっていませんが、
裁判例では、
事故が生じたという心理的嫌悪感は
時間の経過とともに減少し、やがて消滅する
ことを前提していると記載されています。
判例では、
物件内で睡眠薬を大量に飲んで自殺した事件で、
事件発生から5年を経過すれば告知義務はなくなる
としたものがあります。
また、
自殺後・事故後二人目の入居希望者に対する
告知義務は存在しないという判例もあります。
オーナー様からすると、
保有物件で事件事故が発生した場合には、
一刻も早く風評被害が消滅してほしいと
思われると思います。
しかし、入居者からすると、
やはり事件事故のことは教えてほしいと
考えるものです。
今回の新聞記事に記載の内容は、
あくまで参考程度にお考えいただければ
と思います。
この新聞記事での
頑なに理論武装するのはおススメできません。
判例の事実をご理解いただき、
トラブル防止対策をして頂ければと思います。
ルート・イノベーション スタッフブログ